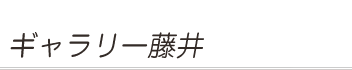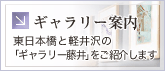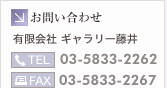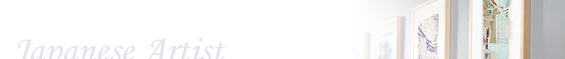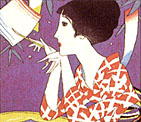 七夕 |
 黒猫を抱く女 |
 やなぎ湯 |
竹久夢二の作風
大正浪漫を代表する画家・詩人で、数多くの美人画を残しています。はかなげで感傷的な女性を描いた夢二の美人画は、当時の女学生のあこがれとなり、「夢二式美人」という言葉を生み出しました。
没後60年を経た現在でも高い人気を誇り、日本各地に彼の名を冠した美術館が存在します。
画家略歴 竹久夢二
竹久夢二 |
1884年 |
岡山県邑久郡本庄村に生まれる |
1902年 |
早稲田実業入学 |
1905年 |
同校の専攻科に進む。読売新聞日曜文壇に投書した「可愛いお友達」が掲載。友人である荒畑寒村の紹介で、平民社機関紙『直言』に、コマ絵が掲載される。また、『中学世界』に応募したコマ絵「筒井筒」が第一賞入選。初めて夢二の筆名を用いる。早稲田実業専攻科を中退 |
1906年 |
島村抱月編『少年文庫』壱の巻の装幀、口絵等を担当 |
1907年 |
結婚。妻・たまきをモデルに「夢二式美人」が生まれる |
1909年 |
たまきと協議離婚。著作『夢二画集 春の巻』刊行 |
1912年 |
『少女』誌に、さみせんぐさの筆名で「宵待草」の原詩を発表 |
1914年 |
呉服橋に絵草紙屋「港屋」を開く。笠井彦乃と出会う |
1917年 |
京都で彦乃と同棲をはじめる。『お江戸日本橋』等、セノオ楽譜表紙の装幀を手がける |
1918年 |
多忠亮によって作曲された「宵待草」がセノオ楽譜から出版。東京に帰る |
1919年 |
佐々木カ子ヨ(お葉)をモデルとし、菊富士ホテルへ通う |
1920年 |
彦乃、25歳で永眠。大阪時事新報に「凝視」の挿絵連載はじめる。「秋のいこい」を描く |
1921年 |
渋谷町宇田川に、お葉と世帯を持つ。福島、会津等に長期旅行し、画会を開く |
1923年 |
恩地孝四郎らと「どんたく図案社」結成を発表するが、9月の関東大震災で壊滅 |
1924年 |
都新聞に、絵画小説「秘薬紫雪」「風のやうに」を連載。アトリエ付住宅「少年山荘」(山帰来荘)建設 |
1927年 |
都新聞に、自伝絵画小説「出帆」を連載 |
1930年 |
銀座資生堂で「雛によする展覧会」を開催。「榛名山美術研究所建設につき」宣言文を発表。 森口多里、島崎藤村、有島生馬、藤島武二らが賛助の名を連ねる。 |
1931年 |
新宿三越で「渡米告別展」を開催、「遠山に寄す」を出品。新宿紀伊國屋書店で「竹久夢二氏送別産業美術的総量展覧会」、京城三越で「竹久夢二氏作品展覧会」、上野松坂屋で「竹久夢生告別展覧会」を開催。「立田姫」を描く。 5月、横浜港より出帆、ホノルルに2週間滞在の後、アメリカへ向かう。カーメルのセブン・アーツ・ギャラリイで展覧会開催 |
1932年 |
カリフォルニア大学ロサンゼルス校、ロサンゼルスのオリンピックホテルで個展開催。9月、サンピドロ港より出帆。パナマ運河経由で、ドイツのハンブルクへ。船中で油彩画「さよならアメリカ」を描く |
1933年 |
ベルリンのイッテン画塾で日本画講習会を開く。9月、帰国。10月には台湾を訪れ、台北市の警察会館で「竹久夢二画伯滞欧作品展覧会」を開催。11月に帰国するが、病悪化し病臥 |
1934年 |
信州富士見高原療養所の特別病棟に入院。最後の装幀本『祇園囃子』(長田幹彦著)が刊行される。9月1日逝去 |
前のページに戻る 画面の上に戻る